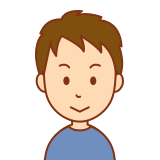
ケーキにジュースなどなど糖質制限が出来ない。どうすれば・・・?
そんなお悩みにお答えします。
今回は発達障害者はなぜ糖質を摂りがちになるのか?起こす体トラブル、対策をご紹介致します。
・発達障害者が糖質を摂りがちになる理由は「ドーパミンの分泌と報酬系」「セロトニンの不足」「感覚過敏」「生きづらさによるストレス」「コルチゾールの増加」「偏った食事」があげられます。
・発達障害と糖質依存の関連性は「ストレスと依存」「特性による偏食」「血糖値の変動」「脳への影響」があげられます。
・糖質依存にならないための対策は「血糖値の急激な変動を避ける食事」「自律神経を安定させる」「専門家に相談」があげられます。
発達障害者が糖質を摂りがちになるのか?
発達障害者はなぜ糖質を摂りがちになるのかは・・・
- ドーパミンの分泌と報酬系
- セロトニンの不足
- 感覚過敏
- 生きづらさによるストレス
- コルチゾールの増加
- 偏った食事
があげられます。それでは順に詳しくご紹介致します!
ドーパミンの分泌と報酬系
ADHDなどの発達障害では、ドーパミンの分泌量の調整がうまくいかないことがあります。
ドーパミンは快感や多幸感を与える神経伝達物質であり、糖質はドーパミンの分泌を促進するため、依存しやすくなる可能性があります。
セロトニンの不足
発達障害を持つ人は、セロトニンが不足しやすく、不安や心配を招く傾向があります。
セロトニンは気分を安定させる働きがあるため、不足すると、それを補うために糖質を求めることがあります。
感覚過敏
発達障害の特性の一つである感覚過敏。
味覚や食感に敏感なため、特定の食品(特に甘いもの)に執着・固執しやすくなることがあります。
生きづらさによるストレス
発達障害を持つ人は、日常生活で困難を感じやすく、ストレスを抱えやすい傾向があります。
そのストレスを解消するために、手軽に手に入る甘いものに頼る機会が増えます。
コルチゾールの増加
ストレスが慢性化すると、コルチゾールというストレスホルモンが増加します。
コルチゾールは食欲を増進させるため、高糖質・高脂肪の食品への欲求を高め、過食に繋がることがあります。
偏った食事
偏った食事:発達障害を持つ人は、偏食や食事に時間がかかるなどの特徴があるため、栄養が偏りがちです。
特に、精製された食品(白米、白砂糖など)は、必要な栄養素が不足しているため、栄養不足になりやすいとされます。
発達障害と糖質依存の関連性
発達障害と糖質依存の関連性としましては・・・
- ストレスと依存
- 特性による偏食
- 血糖値の変動
- 脳への影響
となります。それでは順に詳しくご紹介致します!
ストレスと依存
発達障害を持つ人は、日常生活で困難を抱えることが多く、ストレスを感じやすい傾向があります。
そのストレスを解消するために、甘いものや炭水化物など、糖質を多く含む食品に依存してしまうことがあります。
特性による偏食
自閉症スペクトラム障害 (ASD) の場合、特定の食品に強いこだわりを持つことがあります。
また、注意欠如・多動症 (ADHD) の場合、食事に飽きてしまう、または日によって食べる量が変わる「ムラ食べ」が見られることがあります。
血糖値の変動
砂糖や炭水化物の過剰摂取は、血糖値を急激に上昇させ、その後急降下させるため、情緒不安定や集中力の低下を引き起こす可能性があります。
なので、発達障害を持つ人は、もともと集中力が維持しにくい傾向があるため、砂糖の影響を受けやすいと考えられます。
脳への影響
砂糖といった糖質の過剰摂取は、脳の機能に影響を与える可能性が指摘されています。
特に、精神疾患のリスクを高める可能性や、脳の毛細血管に障害を引き起こす可能性も考えられます。
糖質依存にならないための対策
糖質依存にならないための対策は・・・
- 血糖値の急激な変動を避ける食事
- 自律神経を安定させる
- 専門家への相談
になります。それでは順に詳しくご紹介致します!
血糖値の急激な変動を避ける食事
白砂糖を多く含む食品、揚げ物、加工食品などを避け、野菜、魚、ナッツ類など、血糖値が安定しやすい食品を積極的に取り入れると良いでしょう。
また食事の際には、食べる順番も重要です。食物繊維を多く含む野菜を先に食べ、次にタンパク質、最後に炭水化物を摂ることで、血糖値の上昇を緩やかにすることができるでしょう。
自律神経を安定させる
自律神経が乱れることで、血糖調節能力の低下や、糖への依存を悪化させる可能性があります。
規則正しい生活、十分な睡眠、適度な運動、日光浴などを心がけ、自律神経を安定させられます。
特に、朝起きたら太陽の光を浴びることで、セロトニンの活性化が促され、気分が安定しやすくなります。
専門家への相談
医者の方や専門家に相談することで、的確なアドバイスを受けることができると考えます。
まとめ
発達障害の方はなるべく糖質制限を意識することで、体調が良くなるなど様々な健康効果を得ることが出来ます。
今回ご紹介した方法によって皆様の生活に貢献することが出来たら幸いです。



