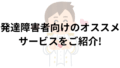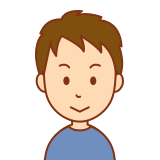
体調不良になりやすい。どうすればいいのか?
そんなお悩みにお答えします!
どうも、ダルグリです!
今回は発達障害者の方が抱えやすい身体の不調とその対処法をご紹介致します!
・発達障害者が抱えやすい身体の不調は「感覚に関わる不調」「消化器系の不調」「運動機能の不調」「頭痛」「体温調節の困難」「空腹感や満腹感の認識困難」「睡眠障害」「自律神経の乱れ」「疲れへの気づきにくさ」「慢性的な倦怠感・疲労」「動悸・息苦しさ」「視覚過敏による眼精疲労や頭痛」「触覚過敏による皮膚の違和感や痛み」「アレルギーや皮膚トラブル」「姿勢の悪さ・体の痛み」があげられます。
・対処法としては「体温調節の困難 ・服装の工夫」「環境整備」「食事・消化器系の不調 ・食べやすい食材の選択」「食事時間の管理」「痛みへの対処 ・自己モニタリング」「騒がしい状況に対する対策」「視覚の対策」「計画的な休憩」「リラクゼーション」「適度な運動」「日光を浴びる」「決まった時間に寝起きする」「疲れの原因を特定し、回避する」「医療機関への相談」「瞑想やマインドフルネス」「趣味の時間」「一人の時間を大切にする」「感情の評価」「タイマーの活用」があげられます。
発達障害者が抱えやすい身体の不調
発達障害の方が抱えやすい身体の不調は・・・
- 感覚に関わる不調
- 消化器系の不調
- 運動機能の不調
- 頭痛
- 体温調節の困難
- 空腹感や満腹感の認識困難
- 睡眠障害
- 自律神経の乱れ
- 疲れへの気づきにくさ
- 慢性的な倦怠感・疲労
- 動悸・息苦しさ
- 視覚過敏による眼精疲労や頭痛
- 触覚過敏による皮膚の違和感や痛み
- アレルギーや皮膚トラブル
- 姿勢の悪さ・体の痛み
となります。それでは順に詳しくご紹介致します!
感覚に関わる不調
発達障害の方は小さな機械音や特定のにおいが気になって体調を崩す、衣服のタグや素材が肌に触れるのが苦痛など感覚過敏の傾向があります。
また感覚鈍麻という暑さや寒さに気づきにくく、適切な体温調節が難しいことがあります。
消化器系の不調
騒々しい場所で緊張して食欲がなくなる、お腹が張って痛くなるなど過敏性腸症候群のような症状が出ます。
また、食事を摂るタイミングが分からず、体重が大きく変動する空腹感・満腹感の認識の困難なケースもあります。
運動機能の不調
発達障害の方は粗大運動(走る、跳ぶ)や微細運動(箸を使う、ボタンを留める)が苦手で、ぎこちない動きになる不器用さ(協調運動症)の傾向があります。
また、脳からの信号と体の動きの連携がうまくいかず、姿勢の悪さ・体の硬さにつながるケースがあります。
頭痛
騒音や明るい光などの刺激が多すぎると、脳が処理しきれずにストレスとなり、頭痛を引き起こすことがあります。
体温調節の困難
温度変化に敏感すぎる傾向があります。
なので、体温調節がうまくできず、不快感や体調不良につながることがあります。
空腹感や満腹感の認識困難
感覚鈍麻や感覚過敏、注意の偏りなどが原因で認識が困難となります。
睡眠障害
発達障害の方は脳の興奮状態が続いたり、漠然とした不安を感じたりすることがあります。
その結果寝つきが悪くなったり、夜中に目覚めたりするなど、睡眠の質が低下しやすいです。
自律神経の乱れ
発達障害の方はストレスや不規則な生活習慣により、自律神経のバランスが崩れやすいです。
その結果、身体的な不調につながります。
疲れへの気づきにくさ
常に周囲の刺激に対応しようとするため、エネルギー消費が大きく、疲れが取れにくい状態が続きます。しかし、発達障害の特性である過集中といった原因で疲れに気づきにくい傾向があります。
慢性的な倦怠感・疲労
常に周囲の刺激に対応しようとするため、エネルギー消費が大きく、疲れが取れにくい状態が続きます。
動悸・息苦しさ
発達障害の方は特性が原因で不安や緊張が高まることがあります。
その結果交感神経が優位になりすぎて動悸・息苦しさの症状が現れることがあります。
視覚過敏による眼精疲労や頭痛
感覚過敏の方が多い発達障害の方。特に視覚過敏の方は明るい光や強い照明、人混みなどがストレスとなり、目の疲れや頭痛を引き起こします。
触覚過敏による皮膚の違和感や痛み
感覚過敏の方が多い発達障害の方。
特に触覚過敏の方は特定の素材の衣服や肌に触れるものが不快で、痒みや痛みに似た感覚を覚えることがあります。
アレルギーや皮膚トラブル
発達障害の特性によってストレスや免疫機能の関連、また感覚過敏による刺激への反応などに悪影響を与えていると考えられます。
姿勢の悪さ・体の痛み
発達障害の方は協調運動症によって不器用さや運動機能の困難を伴うことがあります。
その結果、姿勢が悪くなったり体の痛みを引き起こすことがあります。
体の不調に対する対策
発達障害の方が行うべき体の不調に対する対策は・・・
- 体温調節の困難 ・服装の工夫
- 環境整備
- 食事・消化器系の不調 ・食べやすい食材の選択
- 食事時間の管理
- 痛みへの対処 ・自己モニタリング
- 騒がしい状況に対する対策
- 視覚の対策
- 計画的な休憩
- リラクゼーション
- 適度な運動
- 日光を浴びる
- 決まった時間に寝起きする
- 疲れの原因を特定し、回避する
- 医療機関への相談
- 瞑想やマインドフルネス
- 趣味の時間
- 一人の時間を大切にする
- 感情の評価
- タイマーの活用
になります。それでは順に詳しくご紹介致します!
体温調節の困難 ・服装の工夫
脱ぎ着しやすい重ね着を基本とし、温度変化に対応しやすくします。
環境整備
冷暖房を適切に利用し、快適な室温を保つ。自身の感覚に頼りすぎず、温度計を活用する。
食事・消化器系の不調 ・食べやすい食材の選択
自分が苦手な食感や匂いが苦手なものは避け、食べられるものから栄養を摂るのが重要です。
食事時間の固定
空腹・満腹を感じにくい場合、時間を決めて食事を摂る習慣をつけます。
そうすることで、空腹・満腹に対する対策をすることが出来ます。
痛みへの対処 ・自己モニタリング
なるべく肌触りがいいものを使うなど痛みに対する対処法をしていきます。
その際、自分自身をモニタリングしてどんなことに対して痛みを感じるのか基準を見定めることが重要です。
騒がしい状況に対する対策
駅構内にも騒がしい場所ではノイズキャンセリング機能付きのイヤホンや耳栓を使用して対策を行います。
視覚の対策
強い照明を避け、落ち着いた色合いの環境を整えます。
また、サングラスやブルーライトカット眼鏡を活用する。
計画的な休憩
集中しすぎると疲れに気づきにくいことがあるため、アラームを使ったり、休憩時間をスケジュールに入れたりして、意識的に休息をとる。
リラクゼーション
深くゆっくりと息を吸い、止め、吐くという呼吸法は場所を選ばず手軽にリラックスを促せます。
また、38~40℃程度のぬるめのお風呂にゆっくり浸かり、心身をリラックスさせます。
適度な運動
リズム運動など軽い運動は、セロトニン分泌を助け、自律神経を整えるのに役立ちます。
日光を浴びる
朝起きたらすぐに日光を浴びることで、体内時計をリセットし、セロトニンの分泌を促します。
決まった時間に寝起きする
規則正しい睡眠と食生活を心がけます。
より睡眠の対策をしたい方は専門医に相談することも選択肢に入れます。
疲れの原因を特定し、回避する
何が疲れを引き起こしているのかを把握し、その状況を避ける、または対策を講じます。
例えば、特定の動作が苦手ならそれを避ける方法を検討していきます。
医療機関での相談
体の不調に関してまず医療機関に相談することがオススメです。
話を聞いてアドバイスをもらったりしましょう。
瞑想やマインドフルネス
瞑想やマインドフルネスといった静かな場所で心に集中することで、精神的な安定感を生むことがあります。
趣味の時間
自分の好きな活動(読書、絵画、音楽、ゲームなど)に没頭する時間を作ることで、ストレスを発散し、達成感を得ていきましょう。
一人の時間を大切にする
社会常識にとらわれず、エネルギーを回復させるための一人の時間を意識的に確保していきます。
感情の表現
日記をつけたり、信頼できる人に話したりして、感情を表に出します。そうすることで、ストレスを溜め込まずスッキリすることが出来ます。
タイマーの活用
「〇〇時まで休んで〇〇時に仕事をやり始めよう!」といったことで、タイマーをセットすることで、過集中にならず計画的にメリハリのついた生活を送ることが出来ます。
まとめ
様々な方法をご紹介しましたが、これらの対策を試しながら、ご自身に合った方法を見つけていくことが大切です。
もし今回ご紹介した方法によって皆様の生活がより豊かになれば幸いです。