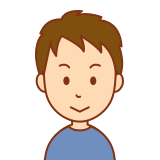
ゲーム依存症になった!どうすればいいのか?
そんなお悩みにお答えします!
どうも、ダルグリです!
今回は発達障害者の方がゲーム依存症になりやすい理由と対策をご紹介致します!!
・発達障害者がゲーム依存症になりやすい理由は「報酬系への影響」「衝動性」「集中力」「こだわりの強さや」「コミュニケーションの困難」「ストレスや不安」「自己肯定感の低さ」「社会的な孤立」「現実逃避」があげられます。
・ゲーム依存症にならないための対策は「ゲームを始める前にルールを決める」「ゲーム以外の成功体験を増やす」「ゲーム以外に関心を持つ」「家族のコミュニケーションを増やす」「「できていないこと」だけでなく、「できていること」に目を向ける」「家族とのコミュニケーションを増やす」「ルールを守れなかった場合のペナルティも決めておく」「ゲームの楽しさや内容に関心を持つ」「ゲームをやる場所を決めておく」「時間管理ツールを使用」「専門機関」があげられます。
発達障害者がゲーム依存症になりやすい理由
発達障害の方がゲーム依存症になりやすい理由は・・・
- 報酬系への影響
- 衝動性
- 集中力
- こだわりの強さ
- コミュニケーションの困難
- ストレスや不安
- 自己肯定感の低さ
- 社会的な孤立
- 現実逃避
になります。それでは順に詳しくご紹介致します!!
報酬系への影響
ADHDの人は、脳内のドーパミン分泌をうまく調整できない傾向があります。
ゲームは短時間で頻繁にドーパミンが分泌されるため、脳がゲームによる快感を強く求めるようになり、依存につながりやすいとされています。
衝動性
発達障害の方は、思いついたらすぐ行動をする衝動性があるとされています。
なので、報酬がすぐに得られるゲームは、衝動性を満たすため没頭しやすくなります。
集中力
発達障害の方は興味関心のあることに過度な集中をすることがあります。
ゲームの場合も過度に集中してしまいゲームに長時間没頭する原因になります。
こだわりの強さ
発達障害の方は強いこだわりを持つ特性があります。
なので、ゲームのコレクションや攻略に深くのめり込み、日常生活が疎かになることがあります。
コミュニケーションの困難
発達障害の方は現実世界での人間関係がうまくいかない、コミュニケーションが苦手といった背景があります。
そういったところからバーチャルな人間関係を築きやすいゲームの世界に没頭する場合があります。
ストレスや不安
発達障害の方は特性が原因でストレスや不安がたまりやすい傾向があります。
なので、ストレスや不安を発散するということで、ゲームに夢中になることがあります。
自己肯定感の低さ
発達障害の方は特性が原因で、現実世界で失敗を重ねるなどして自己肯定感が低いことがあります。
その為、ゲームの世界での成功体験が大きな喜びとなり、それを満たすためにのめり込んでしまうことがあります。
社会的な孤立
発達障害の方は対人関係の困難さから孤立し、孤独感が強くなる傾向があります。
その為孤独感を埋めるためにオンラインでつながるゲームを利用する場合があります。
現実逃避
発達障害の方は特性が原因で現実世界に拒否感を強く持ちます。
その代わりに仮想世界のゲームへ逃避してしまい夢中になりやすく、結果依存症になる可能性があります。
発達障害者がゲーム依存症にならないための対策
発達障害者がゲーム依存症にならないためには・・・
- ゲームを始める前にルールを決める
- ゲーム以外の成功体験を増やす
- ゲーム以外に関心を持つ
- 家族のコミュニケーションを増やす
- 「できていないこと」だけでなく、「できていること」に目を向ける
- 家族のコミュニケーションを増やす
- ルールを守れなかった場合のペナルティも決めておく
- ゲームの内容や楽しさに関心を持つ
- ゲームをやる場所を決めておく
- 時間管理ツールを使用
- 専門機関
になります。それでは順に詳しくご紹介致します!!
ゲームを始める前にルールを決める
ゲームを始める段階で、プレイ時間や課金について具体的に話し合い、ルールを設定します。
設定する場合は、本人と一緒に納得できるルールを考えることが重要です。
ゲーム以外の成功体験を増やす
ゲーム以外の活動(運動、外出、旅行など)に一緒に取り組み、達成感や喜びを感じられる機会を増やします。
これにより、ゲーム以外でも自己肯定感を高められます。
ゲーム以外に関心を持つ
スポーツ、読書、アートなど、ゲーム以外に夢中になれる活動を見つけ、非ゲーム活動を評価する機会を設けます。
そうすることで、ゲームから離れることが出来ます。
家族のコミュニケーションを増やす
発達障害者の方はゲームに頼らない時間を大切にします。
具体的には一緒にテレビを見たり、外出したりするなど、ゲームなしで過ごす時間を増やします。
そうすることで、ゲームに興味を深く持つことが無くなります。
「できていないこと」だけでなく、「できていること」に目を向ける
自己肯定感を上げる為にゲームに夢中になる発達障害者の方。
この場合、何をやるにしても「よくがんばっているね」「ありがとう」といったポジティブな声かけをします。
そうすることで、本人の自己肯定感を高めます。
家族のコミュニケーションを増やす
ゲームに頼らない時間を大切にし、一緒にテレビを見たり、外出したりするなど、ゲームなしで家族と過ごす時間を増やします。
そうすることで、ゲーム以外にも楽しいことを見つけ出して、ゲーム以外を夢中にやることが出来ます。
ルールを守れなかった場合のペナルティも決めておく
ルールを守れなかった場合は、ペナルティを行うことも必要です。
しかし、一方的なゲームの没収は反発を招くため、事前に約束したペナルティ(例:ゲーム禁止期間)を適用していきます。
ゲームの内容や楽しさに関心を持つ
本人がどのようなゲームをしているのか、どんな点が楽しいのかを家族が理解します。
そうすることで、オープンに話せる関係を築き、自分はゲームをやりすぎていると早期の異変にも気づきやすくなります。
ゲームをやる場所を決めておく
ゲーム機やスマートフォンを寝室ではなく、リビングなど家族の目が届く場所に置きます。
そうすることで、途中で注意するなど過度なプレイ時間を避けることができます。
時間管理ツールを活用
ゲーム機やスマートフォンのペアレンタルコントロール機能を利用します。
また、プレイ時間や利用コンテンツを制限する方法もあります。
専門機関
発達障害の特性に詳しい医療機関やゲーム依存症に関する支援センターに相談することで、より適切なアドバイスやサポートを受けられます。
まとめ
ゲーム障害への対処法では、ゲームに没頭してしまうことの背景を見極めて対処することが大切です。
対処法に迷った場合や、ゲームそのものが問題なのか、それともほかの要因があるのかについての見極めが難しい場合などには、専門家に相談してアドバイスをもらうことも一つの方法です。



