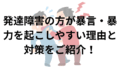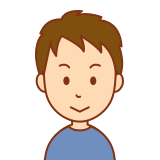
運動音痴な自分をなんとかしたい!
そんなお悩みにお答えします。
どうも、ダルグリです!今回は発達障害の方が運動音痴になりやすい理由と対策をご紹介致します!!
・発達障害者が運動音痴になりやすい理由は「発達性協調運動症 (DCD)」「体幹の弱さ」「ASD」「脳の指令伝達の遅れ」「感覚処理の問題」「運動経験の不足」があげられます。
・運動音痴にならない為の対策は「専門家に相談」「感覚統合療法」「体幹トレーニング」「運動の機会を増やす」「成功体験を増やす」があげられます。
発達障害を持つ人が運動音痴になりやすい理由
発達障害の方が運動音痴になりやすい理由は・・・
- 発達性協調運動症 (DCD)
- 体幹の弱さ
- ASD
- 脳の指令伝達の遅れ
- 感覚処理の問題
- 運動経験の不足
があげられます。それでは順に詳しくご紹介致します!!
発達性協調運動症 (DCD)
発達性協調運動症 (DCD)とは発達障害の一種で、運動や日常動作のぎこちなさや不器用さが目立つ状態です。
縄跳びやボール遊び、字を書くなどの基本的な動きが苦手で、姿勢を保つことや着替えなども困難な場合があります
体幹の弱さ
発達障害者は体幹が弱い傾向があり、姿勢が悪くなりがちです。
体幹は運動の土台となるため、体幹が弱いと、腕や足をうまくコントロールすることが難しく悪影響を与えます。
ASD
ASDの方は、運動を苦手とする傾向があります。
これは、脳内の神経伝達物質の働きに異常があり、脳の興奮と抑制のバランスが崩れていることが運動に対して悪影響を与えます。
脳の指令伝達の遅れ
脳から筋肉への運動指令の伝達がスムーズにいかないことも、運動音痴の原因とされています。
発達障害の方にはこの傾向があるとされ、指令伝達の遅れにより、動きがぎこちなくなったり、フォームが崩れたりすることがあります
感覚処理の問題
発達障害を持つ人は、視覚、触覚、聴覚などの感覚情報を適切に処理することが苦手な場合があります。
その為、自分の体の位置や動きを把握することが難しく、運動がぎこちなくなると考えられます。
運動経験の不足
様々な特性が原因で運動に対して苦手な意識を持ち、自然と運動する機会が減ります。
その結果、運動音痴につながっていくことが考えられます。
運動音痴にならないための対策
運動音痴にならない為の対策は・・・
- 専門家に相談
- 感覚統合療法
- 体幹トレーニング
- 運動の機会を増やす
- 成功体験を増やす
があげられます。それでは順に詳しくご紹介致します!
専門家に相談
専門家(医師、臨床心理士、作業療法士など)に相談し、適切なアドバイスやサポートを受けます。
そうすることで、新しい発見があると考えられます。
感覚統合療法
感覚統合療法は、脳が感覚情報を整理し、運動に変換する力を高める療法です。
バランスボールなどの遊びを通して、感覚統合を促すことができます。
体幹トレーニング
ヨガなど体幹を鍛えることで、姿勢が安定し、運動能力が向上します。
楽しく遊べるような体幹トレーニングを取り入れるとより良いでしょう。
運動の機会を増やす
様々な運動体験を増やすことで、運動に慣れ、動きをスムーズにすることができます。
鬼ごっこなど遊びを通して、楽しみながら運動に取り組むことも大切です。
成功体験を増やす
自分に対して何かしらのミッションを作り運動をしてみましょう。
ミッションをクリアし、成功体験を増やすことで運動が楽しくなり前向きになるでしょう。
重要なのは乗り越えやすいミッションを作ること。いきなりハードルを高くすると挫折する可能性が高くなるので注意しましょう。
まとめ
発達障害と運動音痴の関係について、より深く理解し、適切な対策を考えていくことが重要です。
今回ご紹介した方法が皆様の生活の役に立てたら幸いです。