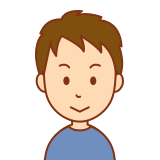
物事を極端に考えてしまう。どうしたらいいのか?
そんなお悩みにお答えします。
どうも、ダルグリです。
今回は発達障害者が白黒思考になりやすい理由と対策をご紹介致します。
・白黒思考になりやすい理由は「あいまいな状況に対する苦手意識」「こだわりの強さ」「マルチタスクが苦手」があげられます。
・白黒思考による困りごとは「人間関係」「自己評価」「日常生活」「学業や仕事」「精神面」があげられます。
・白黒思考の対策は「自分の得意・不得意を把握する」「許容範囲を広げる」「細かく具体的な目標設定」「他者の視点を尊重し、柔軟な考え方を身につける」「思考の切り替え」「共感してあげること」「間違えることに対する対策」「深呼吸・瞑想」「頭の中の情報を言語化」「過去の成功体験を思い出す」「周囲のサポート」があげられます。
そもそも白黒思考とは?
白黒思考とは、物事を「良いか悪いか」「正しいか間違っている」のように二極化して捉える思考パターンです。
曖昧な状況や中間を認めず、極端な判断をしがちで、完璧主義や自己肯定感の低さとも関連があると言われています。こちらは発達障害のASDの方に多い特性とされています。
発達障害者が白黒思考になりやすい理由
発達障害の方が白黒思考になりやすい理由は・・・
- あいまいな状況に対する苦手意識
- こだわりの強さ
- マルチタスクが苦手
となります。それでは順に詳しくご紹介致します。
あいまいな状況に対する苦手意識
発達障害のASDの特性として、あいまいな状況や変化を理解することが苦手な場合があります。
そのため、白黒ハッキリさせた状況ではないと苦手に感じることがあります。
こだわりの強さ
発達障害の方の中にはこだわりが人一倍強いという傾向があるとされています。
そのため、一度決めたルールややり方に固執し、他の選択肢を考えにくくなることがあります。
マルチタスクが苦手
発達障害の方は複数のことを同時にこなすマルチタスクが苦手な場合があります。
なので、一つのことに集中し、他の作業に考慮できず上手くこなせないことがあります
白黒思考による困りごと
白黒思考による困りごととして・・・
- 人間関係
- 自己評価
- 日常生活
- 学業や仕事
- 精神面
があげられます。それでは順に詳しくご紹介致します!
人間関係
相手の言動に対して極端に解釈してしまい、誤解やトラブルの原因になることがあります。
自己評価
自己評価が完璧主義になりやすく、少しの失敗も許せなくなります。
結果、自己肯定感が低下することがあります
日常生活
日常生活で計画通りに進まない場合、パニックになったり、柔軟に対応できなくなることがあります。
学業や仕事
完璧主義的な傾向が強くなるため、仕事や勉強で少しでも失敗すると自己評価が極端に下がります。
その結果、勉強や仕事に対するモチベーションを維持するのが難しくなる傾向があります。
精神面
様々なストレスを抱えやすくなります。
その結果、うつ病や不安障害などの精神的な不調につながる可能性があります。
白黒思考にならないための対策
白黒思考にならないための対策は・・・
- 自分の得意・不得意を把握する
- 許容範囲を広げる
- 細かく具体的な目標設定
- 他者の視点を尊重し、柔軟な考え方を身につける
- 思考の切り替え
- 共感してあげること
- 間違えることに対する対策
- 深呼吸・瞑想
- 頭の中の情報を言語化
- 過去の成功体験を思い出す
- 周囲のサポート
があげられます。それでは順に詳しくご紹介致します!
自分の得意・不得意を把握する
発達障害の方は得意なことと不得意なことをしっかりと理解して把握することが大切です。
そうすることで「自分は不得意だから別に気にする必要はない」といった白黒思考に囚われにくくなる場合があります。
許容範囲を広げる
何かしらの失敗をしても「こんな日もあるか」と許容できるようにしましょう。
そうすることで、白黒思考が和らぐことがあります。
細かく具体的な目標設定
「1日12時間勉強する!」などいきなり大きな目標を立てず、「取り上げず1時間勉強」など細分化し、達成可能な小さな目標を設定しましょう。
そうすることで成功体験を積み重ねやすくなり白黒思考が改善されます。
他者の視点を尊重し、柔軟な考え方を身につける
自分の意見や価値観だけでなく、他者の視点や意見も尊重するなど、異なる見解を受け入れる練習をしましょう。
「完璧じゃなくて良い。努力した過程に意味がある」と捉えるなど、グレーゾーンを受け入れる練習をすることで、より柔軟で現実的な考えができるようになります。
思考の切り替え
何かしらの失敗をしてしまった場合、意識的に別の考え方をしてみるといった思考の切り替えを習慣つけることで、改善が期待できます。
例えば「~な時(状況)はこう」「~な時はこう」と具体的に場合分けして考えることも有効です。
共感してあげること
発達障害のお子様に対して話をよく聞き、気持ちを客観的に見られるように助けます。
特に白黒思考特有の曖昧さに不安を感じている場合は、その気持ちに寄り添い共感することが大切です。
間違えることに対する対策
発達障害特有の「間違えると台無し」という考えが強いお子様の場合は、極力間違わせないように準備をするといったサポートを行なうことが大切です。
また、できたこと・できなかったことを見つけてあげ、「今度はこうしよう」と教えてあげることも重要です。
深呼吸・瞑想
白黒思考になってしまうと焦ってストレスを抱えます。
この状況を打開するために深呼吸と瞑想をしていきます。
そうすることで、白黒思考にならず焦ってしまうことが減っていくでしょう。
頭の中の情報を言語化
白黒思考になってしまった場合、パニックになって冷静ではいられなくなります。
この場合、自分が今どんな状況か気持ちかなど頭の中の情報を紙に書くなど言語化していきましょう。
そうすることで、自然と冷静になりしっかりとした判断がしやすくなります。
過去の成功体験を思い出す
発達障害の方は何かしらの失敗をした場合、過去の成功体験を何でもイイので思い出します。
そうすることで、「まあ次は何とかなる」と失敗したことに対して落ち込みが和らぐことにつながります。
周囲のサポート
必要に応じて心理士などの専門家に相談するといった認知行動療法の支援を受けてみましょう。
また、家族や友人など運動遊びなどで気持ちの切り替えや柔軟な思考を育むサポートをしていくこともオススメです。
まとめ
白黒思考を改善するのはなかなか難しいところだと思います。しかし、この思考を克服することで気持ちが安定すること間違いなしです。
今回ご紹介した対策で皆さまにより良い生活を提供出来たら幸いです。



