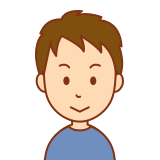
体内時計が乱れる。どうすればイイのか?
そんなお悩みにお答えします!
どうも、ダルグリです!
今回は発達障害者が体内時計が乱れやすい原因と対策をご紹介します!!
・体内時計が乱れやすくなる原因は「多動性や衝動性」「感覚過敏」「朝起きれない」「スケジュールが上手くいかない」があげられます。
・体内時計が乱れることで起こる問題は「不眠などの睡眠障害」「寝たい時間に寝られない」「食欲不振」「倦怠感」「肥満の症状」「認知機能低下」「作業の質が低下」があげられます。
・体内時計を正常化させる為の対策は「自分に合った寝具を使う」「スマホなど誘惑を遠ざける」「感覚過敏の対策」「メラトニンの調整」「日光を浴びる」「運動の実施」があげられます。
体内時計が乱れやすくなる理由
発達障害の方が生活リズムを乱れやすくしてしまう理由は
- 多動性や衝動性
- 感覚過敏
- 朝起きれない
- スケジュールが上手くいかない
となります。それでは順に詳しくご紹介致します。
多動性や衝動性
発達障害の方は衝動性や多動性といった特性があるとされてます。
それが原因で眠れなくなってしまい体内時計が乱れやすくなります。
感覚過敏
発達障害の方は聴覚や嗅覚などの感覚が過敏だとされています。
その為、聴覚過敏の為外が騒がしく感じるなどが原因で眠りたくても眠れず、結果体内時計が乱れることになります。
朝起きれない
発達障害の方はその特性が原因でなかなか眠れません。
それが原因で、朝がなかなか起きられずリズムが乱れてしまい寝坊といったトラブルを起こしてしまいます。
スケジュールが上手くいかない
発達障害の方は約束を忘れるなど決められたスケジュールがなかなか上手くいかないことがあります。
なので、スケジュール通りにいかず生活が安定せず乱れることになります。
どんな問題が発生するか?
体内時計が乱れることで考えられる問題は・・・
- 不眠などの睡眠障害
- 寝たい時間に寝られない
- 食欲不振
- 倦怠感
- 肥満の症状
- 認知機能低下
- 作業の質が低下
があげられます。それでは順に詳しくご紹介致します。
不眠などの睡眠障害
夜に眠れないことで朝起きれず、その後の仕事中や勉強中も眠くなってしまうことにつながります。
結果居眠りをしてしまうという問題を起こしてしまいます。
寝たい時間に寝られない
生活のリズムが崩れてしまうとお昼に居眠りするといった睡眠リズムが悪くなる傾向があります。
その結果、夜寝ようとしても眠気が無く寝られないことがあります。
食欲不振
生活のリズムが乱れることで、食欲が減退するとされています。
その結果、食欲不振につながりなかなか食事がうまくいきません。
倦怠感
体内時計が崩れることが生活習慣が乱れてしまい寝不足などの不調が出てきます。
その結果、体の疲れが抜けないといった倦怠感におそわれます。
肥満の症状
体内時計の乱れはメタボリックシンドロームや肥満といった生活習慣病のリスクを高めます。
その結果、体重増加を招く場合があります。
認知機能低下
体内時計が乱れることで疲労がどんどん蓄積されていきます。
その結果、頭がボーとしてしまい認知機能が低下することにつながります。
作業の質が低下
体内時計が乱れることで頭がうまく働かず集中出来ないことがあります。
その結果、勉強や仕事といった作業効率が悪くなり質が低下することにつながります。
体内時計を正常にするための対策
体内時計を正常にする為の対策は・・・
- 自分に合った寝具を使う
- スマホなど誘惑を遠ざける
- 感覚過敏の対策
- メラトニンの調整
- 日光を浴びる
- 運動の実施
があげられます。それでは順に詳しくご紹介致します!
自分に合った寝具を使う
発達障害の方は多動性などの特性によって上手く眠れないことがあります。
この場合、寝具にこだわって自分に合った寝具を見つけます。そうすることで、眠りやすくなりすぐに寝ることが出来るようになります。
スマホなど誘惑を遠ざける
発達障害の方は衝動性などの特性によって寝る前にスマホを使ってしまうなどの行為をしてしまいなかなか眠れないことがあります。
この場合、自分の周りの誘惑を遠ざける対策をします。
例えば、スマホを遠くの方に置いたり漫画は棚の奥に収納するなど手軽に使えない状況にします。そうすることで、誘惑に負けることなく眠ることが出来るようになります。
感覚過敏の対策
感覚過敏が原因でなかなか眠れず体内時計が乱れる発達障害の方。
この場合、耳栓をつけて聴覚過敏の対策をするなど感覚過敏の対策を行います。
そうすることで、感覚過敏を抑えることが出来て眠りやすくなります。
メラトニンの調整
睡眠を促すホルモン「メラトニン」。
寝る前にスマホやパソコンの画面を見る時間を減らすことで、メラトニンの分泌を促進できます。
また、卵などたんぱく質が多く摂取出来る食事をとることでメラトニンの生成を促してくれます。
その結果、眠りやすくなります。
日光を浴びる
体内時計を治すためには朝の光を浴びることが有効。
朝起きた際、すぐにカーテンを開けて日光を浴びることで、体内時計をリセットすることができます。
また、夜間は目に入る光を減らし、刺激を抑えましょう。
運動の実施
運動をすることで、体内時計がリセットされます。
運動によってセロトニンが活性化され、副交感神経から交感神経への切り替えが上手くいきます。
また、運動によってホルモンの分泌が刺激され、体内時計のズレが戻されるので、正常になります。
まとめ
発達障害の方はその特性が原因で体内時計が乱れる傾向が強いと考えられます。
今回ご紹介した方法で皆様の体内時計を正常化させることが出来たら幸いです。



