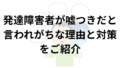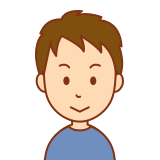
留年してしまった。こうならないためにどうすればいいのか?
そんなお悩みにお答えします。
どうも、ダルグリです!
今回は発達障害者が大学など留年しやすい理由と対策をご紹介致します!!
・発達障害者が留年しやすい理由は「不注意・集中力の持続困難」「計画性の欠如」「興味が極端」「マルチタスクの苦手さ」「自己管理の課題」「メンタルヘルスの不調」「対人関係の悩み」「環境変化への不適合」があげられます。
・留年しない為の対策は「障害学生支援窓口への相談」「合理的配慮の申請」「特性の理解と受容」「具体的な行動計画」「生活リズムの改善」「特性に合った学習方法の実践」「自己モニタリングと早期対応」があげられます。
発達障害者が留年しやすい理由
発達障害者が留年しやすい理由は・・・
- 不注意・集中力の持続困難
- 計画性の欠如
- 興味が極端
- マルチタスクの苦手さ
- 自己管理の課題
- メンタルヘルスの不調
- 対人関係の悩み
- 環境変化への不適合
があげられます。それでは順に詳しくご紹介致します!
不注意・集中力の持続困難
発達障害の方は衝動性など授業や課題に集中できないことや重要な連絡事項を聞き逃すことがあります。
その結果、単位を落としてしまい留年につながります。
計画性の欠如
発達障害の方は計画性が無いとされています。
その為課題の提出期限を忘れたり、レポートを計画的に進められなかったりします。結果単位が不足してしまい卒業できない事があります。
興味が極端
発達障害の方は興味の偏りが極端だとされます。
なので興味のない授業に出席できず、単位不足につながることがあります。
マルチタスクの苦手さ
宿題を行なったり部活を行うなど様々なマルチタスクが発生してしまう事があります。
その結果、提出物が提出出来なかったりと上手く単位が取れず留年につながります。
自己管理の課題
発達障害の方は自由度が高くなる大学生活において時間管理や自己管理がうまくいかず、生活リズムが崩れてしまうことがあります。
その結果、体調を崩すなど休みがちになり単位が取れず留年につながります。
メンタルヘルスの不調
発達障害の特性が原因で失敗体験の積み重ねや、周囲とのコミュニケーションの難しさから自己肯定感が低下し、精神的な不調をきたす場合があります。
その流れでうまく勉強出来ないなど様々な弊害が生まれてしまい留年する可能性が高まります。
対人関係の悩み
発達障害の方は、コミュニケーションのずれわ対人関係の構築が苦手で、孤立することがあります。
また困ったことがあっても、相談先がわからなかったり、「どうにかなるだろう」と考えて放置したりすることがあります。
環境変化への不適合
高校までと違い、大学は時間割や課題管理をすべて自分で計画する必要があり、この構造化されていない環境に適応することが難しい場合があります。
留年しない為の対策
発達障害の方が留年しない為の対策は・・・
- 障害学生支援窓口への相談
- 合理的配慮の申請
- 特性の理解と受容
- 具体的な行動計画
- 生活リズムの改善
- 特性に合った学習方法の実践
- 自己モニタリングと早期対応
になります。それでは順に詳しくご紹介致します!
障害学生支援窓口への相談
大学などの学校には障害学生を支援する窓口があります。
早めに相談し、自身の困難な点や必要な支援について伝えましょう。
合理的配慮の申請
講義の資料を事前に配布してもらう、試験時間の延長、レポートの提出期限の調整など、自身に合った支援(合理的配慮)を具体的に申請します。
そうする事で、過ごしやすくなり留年する可能性が低くなります。
特性の理解と受容
自身が発達障害の特性(例:忘れ物が多い、集中力が持続しないなど)を理解し、それとどう向き合っていくか、自己理解を深めることが大切です。
そうする事で、自然と自分に合った対策を実施する事が可能です。
具体的な行動計画
授業への出席、課題の提出、試験勉強など、具体的な行動計画を立て、視覚的にわかりやすいように記録するなど工夫をします。
そうする事で、忘れる事なく留年する可能性が低くなります。
生活リズムの改善
健康的な食生活、十分な睡眠、適度な運動は、集中力やメンタルヘルスを保つ上で不可欠です。
特に衝動性の特性がある場合、生活習慣が乱れると学業に影響が出やすくなります。
生活リズムを自分の特性に合わせていく事が大切です。
特性に合った学習方法の実践
視覚優位の特性がある場合は、視覚教材や図解を積極的に利用など自分の特性あった学習方法を実践します。
また、授業内容を追いかけるのが難しい場合は、事前に講義概要を確認したり、録音した講義を聞き直したりします。
そうすることで、勉強についていけるようになり何とか留年する可能性が低くなります。
自己モニタリングと早期対応
発達障害の特性により、学期末に突然成績不振になる事があります。
この場合、学期の早い段階から、自身の成功・失敗パターンを把握し、対策を立てます。また、不安や困難を感じたら、早めに周囲に相談します。
そうすることで、立ち直ることが出来て留年する可能性を比較する事ができます。
もし留年を経験した場合
留年を経験した場合は↓↓↓↓↓
・悲観しすぎないこと
自分の特性と向き合い、卒業に向けてどうすればよいかを考える良い機会とポジティブに捉えましょう。
・専門家の助言を求める
休学を経て復学する際には、専門家や支援室と連携し、具体的な復学プランを立てます。
自身の状況を受け入れ、解決策を模索することで、卒業までプロセスがすぐに見つかります。
まとめ
発達障害の方は留年しない為の、自分の特性を理解した対応をする事が重要です。
今回ご紹介した方法によって皆様の留年しない為の工夫につながれば幸いです。